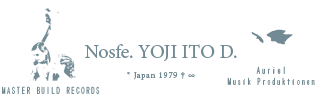
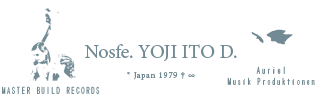
|
|
🕯 言葉の肖像 第一部
作/著 伊東 洋司
言葉の肖像 第一部 (西暦二〇一九年――元号・令和元年九月一日)

_______
“ エーデルワイス - Edelweiss. とともに... ”
_______
序言 わたくしの内部から沸き起こる芸術としての感性は、八歳のときの「音楽」との影響から、足並みをそろえ芽生えるはずであったのだけれども、わたくしを取り巻く時代背景、もしくは世俗的なことから、自己の芸術的内向は外部によって封じ込められてゆく、もしくは自ら封じ込めなくてはならざるをえないといった、そういう内的な働きや外部の影響がどれほどの芸術および芸術家を業界は封じ込めてしまったのか。つまり、「芸術家とともに、またその芸術家によって、自己の教養にいそしんできた人々に、さらに教養のかてとなることは必定ではないのか」ということから考察し反省すべく、ここに、「芸術としての音楽」を焦点に短篇の自伝をくわだてたのである。ここでひとつ、Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) の自伝『わが生涯から 詩と真実 - Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit (1811)』にある序言の一部をかかげておきたい。
「(•••)伝記の主要な課題が、人間をその時代関係のうちに描き出し、全体がその人間にどの程度杭い、どの程度幸いしたか、またどのようにしてその人がそこから世界観や人間観を作りあげたか、その人が芸術家、詩人、著作家であったら、その世界観、人間観をどのようにふたたび外に向かって映し出したかなどを示すことだと思われる。しかしそのためには、これはほとんど望みがたいことだろうが、個人は自己と自己の時代を知ってかからねばならず、また自己はあらゆる境遇のもとでどれくらいまでいつも同じ自己であったかを知り、また人間をいやおうなく拉し去り、規定し、形成するところの時代を知ってかからなければならない。たれでも生まれるのが、十年早いかおそいかのちがいで、その人自身の教養や他人にたいする影響からいって、まったく別個な人間になっていなかったとはいえまい。」――参考にした訳書は次の通り。/『ゲーテ全集 九』«初版»、人文書院、菊盛英夫訳、一九六〇年(昭和三十五年),pp.九頁に詳しい。
こうして、ようやく記述するにいたったこの短篇からなる回想と考察は、ほんの一部分ではあるけれども、いわゆるどこにでもいる少年と少女であり、だれもが同じくして経験し、体験する日常の記録である。しかしそこには、周囲の環境といったものから、なにものにも誘惑されず、支配されず、純粋な教養(芸術)とともにいそしんでいった物語として、それはおよそ愛情、温かさ、豊かさ、感性、充溢といったものを受け入れ、価値ある真実とともに情熱と偉大さを、そうして、陶酔と明晰との調和をどうか忘れずに、『古典』と『ロマン』このふたつの形式を思慮深く利用しとどめておくということが、それぞれの時代におけるもっとも評価されるべき、もっとも純粋である精神性の一環として、また、こうしたすぐれた意思と忍耐を持ってこそ、これからの世界観や人間観を作り上げていくのには極めて重要なことであったのではないか。
――注:ここで登場するそれぞれのアーティストおよび名称は、物語の一環としてあげているものであって、自己の名利ではないこと、そして、批判するものではないことを念のため申しておく。――
_______
 『詩人よ、語るな、書け、』
-Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
/ 龜尾英四郞訳
_______
第一章:〇~十一才初恋夕暮れ
一九七九年一月七日(昭和五十四年)、正午の十時十分をすぎたころに、わたくしは大阪府豊中市にて双子の末っ子として誕生する。その後、大阪にある母の実家から、当時の住まいである東京都武蔵野市へともどり、そうして、わたくしが三つのときに、千葉県佐倉市へと移り現在にいたるわけで、それにしても、わたくしが武蔵野市吉祥寺で演奏会を開くことができたのも、こうした縁があってのことなのだろう。当時の武蔵野市でのことは、一コマづつでしかおぼえていることはないのだけれども、母が自分たちを自転車にのせて、デパート(東急)まで買い物に行くとき、当時まだ開店したばかりであった、いつもの演奏会場のすぐ側を通っていたことを思うと、なにか不思議な気持ちになるものである。その後、移り住んだ佐倉市もまた変わっていて、当時はまだまだ田舎であることから、暮れ方になると、近所にあった神社の鐘の音が響き渡り、その神社のすぐ近くには小さな牧場まであって、空気の匂いも、家から外へ出ればその牧場の匂いがつどつど漂ってきたりと、まったく今では考えられない光景が広がっていたものである。少し離れて辺り一面、小学校までつづく広い範囲におよんで開発途中であることから、小さな雑木林やらため池やら、工事前の空き地が広がり、子供にとっては恰好の遊び場となったのである。父も、こうした自然の環境を子供たちに見て、感じてもらいたくてこの場所を選んだといっていたのも、こうした環境が、都心を中心とした交通の便宜を考えた場合に、まだユニークで貴重な場所であることを知っていたのである。
さて、こうした著しい環境の変化とともに、わたくしは今、エレクトリックギター奏者としてひとり芸術活動を展開しているわけであるが、わたくしはもともと幼少のときより音楽好きで、それは毎週日曜日の朝、いつものアニメ(当時は、キン肉マン・テレビアニメ 1983-1986 が放送されていた)がはじまるまでの間に、クラシックや童謡などのレコードを長男の兄に掛けてもらうのが密かな楽しみであったのだけれども、母も若いときより洋楽好きということから、Elvis Presley (1935-1977) や The Beatles (1960-1970)、Michael Jackson (1958-2009) 、あるいは Pat Benatar (1978- ) など、ロック音楽の様式も幅広くよく流れていたもので、少年になったばかりのわたくしには少々刺激の強かった Madonna (1958- ) も初来日ということで印象に残っていたり、なかでも、ビデオデッキがわが家に設置されたのもこのときで、Michael Jackson から『Thriller (1983)』のミュージック・ビデオを母が購入してからというもの、毎日のように見ていたように思いだし、まだ幼いわたくしは、怖いとときどき目をそらしつつ、「オオカミ男や死体に囲まれてもマイケルは味方だ!」と勝手に思いながら、歌やダンスがはじまると、怖いことは忘れて無邪気に楽しく観ていたものである。また、日本の歌謡曲も父の好みから、今も加山 雄三 (1937-) などよく耳にし、当時放送されたばかりの『加山雄三ショー (1986-1989) 』は、父とよく見た唯一の音楽番組で、『ザ・ベストテン (1978-1989) 』も、長男の兄の好みからだったのか、テレビからは、自分たちが寝る時間ぎりぎりまで毎週のように、毎日のように流れていたのである。
とにかくアメリカの報道機関 Billboard (1894-) を中心に、テレビやラジオ、オーディオ機器を通じて音楽に影響されていたわけである。そう、有名なチャリティーソング、“We Are The World” (1985) が放送されたのがちょうどこのときになり、しばらくそれが立て続けに毎週流れていたことから、さまざまなアーティストを知るきっかけにもなったもので、そのなかでも、わたくしにとって Bruce Springsteen (1949-) や、Cyndi Lauper (1953-) の歌う、あの力強い姿勢と歌声は、とくに印象的であったのをよくおぼえている――それとは対照的に Bob Dylan (1941- ) は不気味であった!――。こうして音楽とともに毎日をすごしているうちに、いつしか自分で思いついたメロディーを面白おかしく、ところかまわずに次男とともに楽しくよく歌い、陽気に遊んでいたのであった。そうした幸福のなか、「音楽」というものに形をもって意識しはじめたのは七歳ごろからのときで、わたくしの音楽の才能は、小学三年のときの、当時の担任であった岩井 弘子先生との音楽の授業で日の目を見ることになるのである。
このときのことはわたくし自身もよくおぼえていて、とにかくその自然からでる表情の豊かさである。そのほかの科目はからきしだめであるのに、なにも難しいことはなく、譜面から音とリズムを表現豊かに再現してゆくのであった。それは、「カッコウ - Kuckuck, Kuckuck ruft´s aus dem Wald. - by August Heinrich Hoffmann (1798-1874) 」という曲を、気がつけば先生が嬉しそうに、それもみなの手本のように幾度もわたくしに歌わせるものであるから、わたくしも得意げに歌ったものである。授業を終えた後もほんとうに気にいられたようで、初めてのアンコールもいただき、岩井先生もわたくしの普段の成績の乏しさから安心したのか、そのときの励ましと喜びの声は、今も忘れることはない。それからしばらくして、今度はリコーダーによる発表会がはじまると、そのとき教材として選ばれた曲が、アメリカで有名なミュージカル、『サウンドオブミュージック - The Sound of Music (1965)』の挿入歌で、当時からとても甘美で美しいメロディに感じられた「エーデルワイス - Edelweiss. 」であり、わたくしの演奏は、その豊かなリズムと音色から、すでにほかとは明らかに突出した感性によって、自分でも何か才能というものがあることに気づきはじめたのである。それは、疑いもなく「芸術」に要するための純粋さと繊細さであり、わたくしはまだ少年になったばかりでありながら、その美しい抒情的なメロディーによって、無邪気さや単純さとは別の、ある二つの胸の思いが無意識のうちに、わたくしの内部から滲みでていたのである。
それにしても、今現在のわたくしのまわりでは、子供たちが大人顔負けに音楽を演奏したり、演技やスポーツなど披露している放送や動画などがこの数年の間によく見かけるようになったもので、そういったことから、ここに所見を記しておくが、わたくし自身のこのときの演奏はいわゆる天才児とはまったく別格のもので、自然の状態によって素直に「歓び」といった感情がえられるようになるには、リズムからなる強弱やテンポの緩急といったものから、メロディがまるで生きているかのように、決められたリズムとテンポのなかで自己の音色、自己のテンポを見出すのである。つまり、訓練されたものや模倣などとはまったく別の、即興によるもの、心的な生成と生起の感情から現出するものであるということである。これは、いわゆる技術的なこととは全く無縁の、心的事象による体験と経験によってのみ成せる「克服」といった概念からなる現象で、ゆえに、幼児から少年期にかけての作品は、直観的であっても芸術としては全き不十分であるのはこういったことからで、つまり、自然を意識するということから残酷性、古典をまだ知らないからである。とはいえ、ごく稀に、ゲエテやフルトヴェングラーなどのような、いわゆる天才を超越した、自然に対する意識を明確に持ち合わせた能力(本能)の存在、つまり魔神的資質によって年齢問わずに垣間見ることがあると述べておこう。
*
さて、これから始まる恋物語は短いけれども、今も当時と変わらずに時々に思い出し、自分はまだ幼児であったにもかかわらず、わたくしにとって最大の体験として記憶しており、目撃したことである。最初に登場するその少女(正確には幼女である)の後髪は長く、前髪は短くそろっていて、目は大きくてやさしい面影があるのだけれども、決まってこうした印象しか残っていないからといって、だれもがそうであるように、小さなものを大きくし、細かいものはおおざっぱにしてしまうというのは、まあ卑俗な大人のみる人間的世界であって、子供たちにとってはこれこそが純真な世界なのである。しかしながら、まだ幼少であるにもかかわらず、こうした初恋とは誰もが経験し、体験してゆくものなのであろうか? そうしたことはわたくしに特別知ったことではないけれども、わたくしが今記憶している限りのことをここに留めて置くということは、瞬間といった大切さを知らせることなのである。いま、生死に怯えながら歪んだ愛*に飢えている人人に、一体どのような瞬間を記憶してゆくのか。そのような人人に、わたくしのような芸術的“瞬間”――これを光に例えてもよいだろう――を捉えることはできるのだろうか。
極小さなこの瞬間の物語も、この幼少期の少女にたいする小さな純愛(初恋)が芽生えはじめるのも、その当時の記憶というものは突然はじまり、突然おとずれ、突然終わるのであった。 それは、幼稚園での楽しかった二人だけの追っかけっこからはじまり、自分は走りながら両手を鋏のように大きくひろげて捕まえようとするのを、その少女は楽しそうに逃げては自分に捕まりそうになると何とか振り払い、教室から廊下へ、そして隣の教室へと逃げまわるのであった。そうして休み時間が終わると、お互い隣り同士の席に座り、顔を見合わせながら無垢に抱きしめる。こうしたほんとうに楽しかったちいさなきっかけが、まだ三つでありながらも純潔といった精神的、道徳的なもののうちに、少女にたいする胸の想いに馳せてゆくのである。その少女の住まいも近所であるから、一度だけ、遊び仲間と三人で家に招かれ、少女の部屋で遊んだこともあった。ただ、そのときの少女の住まいと部屋の印象は変わっていて、なにか中世の洋館のようで中は暗く、部屋も、太陽は姿を見せずに薄暗い。また、三角の形をしたような天上も低く感じられ、とにかく暗くひっそりとした不気味な印象しか残っていないのである。こうして、早くも初めての女性との日々の楽しみから、胸の高鳴りのようなものを感じ始めたとき、突然の少女の転園という、意地悪な天使のいたずらなのか、お別れとなってしまったのである――まだ幼い自分は、きっと夢かなにかと混同してしまったのであろうか。そして今現在もその住まいは当時と変わらずに残されている。ただ、どの住まいであったのかがはっきりと良く思いだせないのだ。わたくしは、今もそこにたたずむと、夢の中に強く引き込まれるような感覚に、えもいわれぬ深い哀感が漂い、それは真に幽玄である――。
この最初のちいさな「悲劇」は、面影だけが残り、あとになって母や遊び仲間に少女のことを何とか聞きだそうとしても、誰かもなにもわからないといった始末で、名前も、文字すらまだ覚えるというにはおぼつかない年齢では、しっかりと記憶するということにまでまだいたらずに、しかし何とか名前を忘れまいとかろうじておぼえていた時期もあった。しかし転園ということから、名前一切が幼稚園から出てこなくなってしまったことで、よく思いだせなくなってしまったのだ――もし果物や何か甘いものを連想するような名前であったらきっと忘れないでいたのだろう。例えば、同じ組にいた“ななえ”という少女の名前を知ったときの印象はとても強く残っていて、それは果物の“ばなな”を連想させたものだし、容姿も髪が長く、どことなく似ていたような気がしていたからなのだ――。当時の住所欄を探してみても、年長クラスの住所欄しかなく、卒園アルバムも当然転園したことで残されていないため、結局、少女のことが写真一枚すらどこにも残されていないことがわかると、何もかもが幻であったかのように思え、しかし、こうした瞬間によって、逆に芸術的感性につながる精神と悟性との調和とは、一種独特な感性を持つ小さな芽生えにもなったのである。またふしぎなことに、当時のわたくしは淋しさよりも、また会えるということが何となく分っていたのである。つまり驚くべきことに、幼少にして予覚というものをすでに信じていたのであった。
こうして三年後、なんと、待ちにまったうれしい一通のお知らせが幼稚園から届くのである。それは、わたくしが小学二年のときに、当時の園児を集めた「お泊り会」といった企画に招かれ、夕暮れ時に初恋の少女と再会することが出来たのだ! もちろん少女も自分のことをおぼえていて、お互い恥ずかしそうに笑顔で、簡単な挨拶だけだったようだけれども、再会に心からの喜びを感ずることが出来たのである。こうして突然のお別れから、この「お泊り会」を期に、待ちにまった再会が叶い、それから一晩中、わたくしはなにか微妙な不安とあせりをおぼえつつ――この再会のあと、別々のグループとなり、なぜかどの部屋にも少女を見つけることができなかったのだ。そして、夕暮れの一台の車である。それが実に妙であったのを思い出していた――、少女のことをもっと知りたい、もっと一緒になりたい想いでいっぱいになり、どうにか眠りについたものである。そして次の日の朝、ずっと遠目で探していたのだけれども、どうしても見つからず、似たような雰囲気の少女をみつけては、別の少女であることにあせる気持ちが増してゆき、結局、その一回きりの再会で、初恋の少女とは最後となってしまったのである。おそらく、実家が遠いために、前日の夕暮れでの再会の後に帰ってしまったのではないか、それも、自分と会うためにわざわざ来てくれたのだと、今のわたくしはそう思わずにいられないのであって、しかし、当時の自分がそのような考えもつことなどありえず、ひたすらに淋しく、まるでほんとうの神隠しにでもあったかのように、まわりはだれもなにも気にせずに遊びに夢中になり、わたくしはこつぜんと消えてしまった少女のことを、だれにも知れずに、そしてなぜか、少女の顔も声も、名前すらも、なにもかもがよく思いだせずに、ひとり最後まで探していたのであった。
*
雪
こうした体験からわたくしは、初恋の少女を求めるあまり、その恋による連関と多様な呼応と変化、天と地というものは、まるで入れ替わるようにして錯綜をもたらし、また、あのいたずら好きの天使は、自分を責苦にあわすのである。それは、自分より少し小柄で、赤色がとてもよく似合い、髪の長さは首あたりの中間、その小さな顔つきから、ふっくらとしたほほに、かわいい笑顔と口元がとくに印象的であった、風変わりな少女リア――ここではリアと呼ぶことにしよう――と出会い、そうして、あの日とは全く逆の立場から新たな恋は訪れ、この風変わりな少女リアとの最初のきっかけも、突然に、「偶然」が引き起こすのであった。
それは、ある日の全校集会で校庭に集まった日のこと、ありふれたように遊び仲間でふざけ合っているなか、わたくしは友人に後ろから抱えあげられそうになったことから、自分も仕返しにと思い、うしろに回って腰に手をまわし、抱きしめたのであるが、感触がなにか細く、やわらかく軽い印象であったことから、そこからさらに抱き上げてしまったのである! そうして、まわりのざわめき様に、ようやくそれがリアであることに気づいたときには、リアは驚いて向きを変えていたものであるから余計にからかいやらなにやらに囲まれ、お互い顔を赤らめながら恥ずかしい思いをしたのであった。こうして、次の日の朝、わたくしはなにくわぬ顔で学校の正門をくぐろうとしたその途端に、なんと、リアがまわりを気にせず、自分に走り寄って抱きついてくるのであった! それが風変わりな少女のゆえんで、また容姿もとても可愛いものであるから、なんともわたくしは恥ずかしく、わざと嫌がるようにそぶりを見せつつ手を払い、ふたりで走り回りながらそのまま教室まで逃げてゆくのであった。それは、あの初恋の日の小さな純愛を思わせる、恋の再来であったのだ。もちろん、リアが初恋の少女だったのではないかと疑うほどで、それは、ほとんど無条件といってもいいほど、瞬間的にリアに惹かれていったのである。しかし、わたくしは追われる立場からどうすればよいのか全くわからぬままに、そのようなことが何週間と続いてゆくにつれ、リアもあきらめてしまったのか、お互いの距離もだんだんと離れてしまったのだ。逃げまわっていた自分にたいして当然そうなるように、ついにリアは、また逃げようとしてしまう自分に「もうしないよ..」と答えて、つまらなそうにそっぽを向いてしまい、こうしてその後は、ときどきリアはふざけ半分で走り出そうとする構えをとるだけで追ってはこなくなり、わたくしはようやく自分の過ちに気づきはじめ、どうしたらまたあの一時の仕合わせを取り戻すことが出来るのか、しかし、自分とリアは、まだ幼少のうえに、当然に会話もまだおぼつかず、あの偶然の出来ごとからであるからまた後ろから抱きあげるというわけにもゆかずに、もう一度近づくことがどうしても出来なかったことで結局、リアとは遠のいてゆくのであった。こうして、胸の内に想いを秘めたまま、クラスもその後、三学年、四学年には別となってしまい、そうして小学五年となったとき、わたくしの想いは、当然変わらぬままに、ようやく同じクラスとなったのである。
おそらく、小学最後の担任であった山中 ふく子先生は、自分のリアを見る目とそわそわした態度に気づき、わたくしの胸の内をなんなく知ったのであろう――そのときの様子は、大人から見れば可愛い純情な子供の行動とはいえ、当時のわたくしはまるで醜態であったのだ!――、小学五年のある雪の日、そう、バレンタインが近づこうとする日である。だれかの提案であったのか、山中先生は、男女同士のツーショットを撮るために、校庭でばらばらとなって遊んでいる自分たちを探しだし、見つけてはペアを選び撮りはじめ、そうしてつぎに、自分とリアを水泳場際まで呼びとめ、そこで二人だけの写真を撮ってくれたのであった!――後にも先にもこの恋物語で手助けをしてくれたのは、山中先生が撮ってくれたこの写真だけであった――しかし喜びもつかの間、そのときのリアの様子は、なにか複雑で、物静かに、ただ、笑顔を見せることのない大人びたものを感じたのである。自分も最初は恥ずかしさがあったのだけれども、不思議なほど落ち着いているふうなリアを見たとたんに、微妙な距離というのか、しかし、横に並べば不思議と落ち着くことのできる「空気感」を、リアから感じ取ったのであった。
ところで、そのときの写真は、しばらくのあいだ何十年も手元の引き出しにしまい込んであったのだけれども、十八歳のときの「犠牲の失恋」がきかっけで、アルバムに戻してしまった。その写真を今思い返してみると、雪の日、空は濃い曇り模様で、わたくしはリアと比べ、いつの間にやら背も低く、自分がまるであの三年前の「偶然」に取り残されているかのように、余計に幼く見える。しかしながら、その写真は今のわたくしにとって、白く輝く、小さなエーデルワイスのように見えるのは、そう、写真を撮るとき、わたくしはリアのすぐ隣で、初恋とともに三年前のことを思いだし、そのことをリアともう一度話したい想いでいっぱいだったからだ。
こうして、バレンタインでは義理ということで決着がつき、リアからは、ほかに好意を寄せている人がいるような旨を聞かされたことで、どこにでもある失恋のように、あっけなく終わるはずであったのだけれども、ところがある日の放課後、さらに悪いことに、クラスの人気者といった仲間から、なにか意地悪そうに、わたくしはからかわれながらある事実を聞かされることになるのである。それは、リアととても仲の良い少女が、自分に恋心を寄せているというのであった! しかしそれは、わたくしにとって恐れていた事態でもあったのだ。わたくしは、そのリアの友人としばらく席が隣同士であったことから、話してみれば相性がとてもよく、それが本当に楽しくて、仲よく会話をしていた時期があったのだ! このときのおしゃべりは、自分でも全くふしぎなくらい自然で大人びた、今でもそれ以上の楽しい会話を女性としたことがないほどで、ままごととは全く違う、初めて「女性」と会話をしたといえるのがこのときであったのである。しかし、リアのこともあって、当時の自分にはどうしてもその少女からは恋愛感情が湧かず、席が離れてしまうと今までのことが嘘であったかのように、それっきりとなったのである――正確にいうと、魅惑というものから自分は距離を置いたのである――。しかし、このことがきっかけで、その少女にとっては、おそらくわたくしが初めての恋となったのであろうか、つまり、その少女の前でわたくしは、リアを追いつづけていたこと、そして、まだ自分は子供とはいえ、ふたりの間のことをなにも考えず、哀しく辛い思いをさせていたこと、さらに、リアとのことで醜態をも見せてしまい、そしてなにをすることもなく、また、やわらげようにも恋の術というものを学ぶような機会など当然なく――恋に学ぶ術などあろうか!――、結局その後、なにも出来なかったわたくしの臆病さと愚かさを後にふり返り、まざまざと自分自身の醜態を見ることになるのであった。
その冬の季節、その少女がわたくしにいった言葉と表情、そして声は、今も鮮明に胸に刻みこまれている。それは、軽く微笑みながら、なにかを我慢しているかのようにもみえ、しかし、やさしくこう答えるのである。「知ってるよ リアのことが好きなんでしょう... わかってるんだから! 」と、あのいつもの、透きとおった綺麗な白い服の少女は、自分にそういい残したのだった。
*
これを最後に、わたくしの恋物語は完全な終わりをつげ、内部で刻は止まり、その後は、まるで悪魔による連鎖が響き渡るかのように情事に導かれ、純真であればあるほど、まわりの成長からとり残されているかのようにうまくゆかず、辛い目に合っては合わせ、こうして今現在も、首にかけられた呪いの鎖は、何度となく重くのしかかるのである。しかしやはり当時まだ子供である。その子供の単純さは、楽しいときは楽しみ、悲しいときは泣き、日が過ぎればそのときのことは忘れて、次のことにいつも夢中なのだ。しかし、わたくしの止まってしまった胸の想いは、決してだれにも外に出すことなく、心をくらましながら、ずっと、自らのうちに孤独にさいなまれていたのである。
こうして、わたくしの周囲の技術的、科学的な(世界考察による)環境の変化などに加え――このことは後に考察として述べるとしよう――、また、友人達との関係からも、わたくしの周囲では楽器を演奏するということが女々しいといった風潮もあり、大好きな音楽とは仕方なく距離を置かざるをえず、さらに、わたくしの致命的な臆病さも加わってからというもの、吹奏楽部に入ることも叶わずに、清らかな青春の恋物語が終わりを告げたように、自らの「音楽」にたいする才能は、「音楽」という授業が専門学科としてとり扱われてからというもの、わずか小学三年の八歳のうちに閉ざしてしまい、そうして、まわりの教育の在り方に、つまり、成果と発展をのぞむかぎり、わたくしの内向はまわりの期待といったもの、成績や勝敗といったものを無条件に要求するような在り方についてゆけずに、また、周囲の環境から完璧さや正確さを求めるあまり、ついてゆけていない者にはまわりから貶められ、必然とかれらの、ロマンを誹謗した知的妄想による「高ロマン」に、わたくしは知らずのうちに飲み込まれていってしまったのであった。
――これらの恋物語のつづきをここで回想することは、芸術および教養においてとても大事なことではあるのだけれども、あまりに長くなりすぎるうえに、わたくしはそもそも物書きではなく、こうして物を書くこと自体、はずかしながら素人(ディレッタント)であるからして、ここから先は「音楽」のこともあるので控えさせていただきたい――
_______
第二章:十二~二十四才餓鬼 わたくしが十歳になるころには、ラジカセやウォークマン、記録媒体である CD が Vinyl(レコード)を抜いて普及しはじめ、十一から十二歳となるころには、世界情勢では湾岸戦争 (1991) が勃発し、そのニュースを自分は教室のテレビで一部始終を見ていた記憶がある――本当であればこの戦争のことについて書き加えるべきであろうが、ゲーテが生きた時代とは違い、現代では映画による伝記や、インターネットによって情報化されている時代である。検索リンクを設けておいたので時間があれば個々でいきさつなどを調べていただきたい――。さて、子供にとっては不可解な出来事がテレビで流れていた、そのようなころである。長男の兄が好んでよく聴いていた日本のポピュラー音楽への影響もあって、自分にも次第と日本のロック音楽のほうへと意識されはじめてゆくなかで、小学もいよいよ卒業となり、中学へと入学した一九九一年のクリスマスの日、いよいよ転機がおとずれる。それとなく兄たちと聴いていた日本のロックバンド、 BOØWY から、十枚組のアルバム『BOØWY COMPLETE LIMITED EDITION』を兄が購入してからというもの、ますます日本のポピュラー音楽にのめり込んでゆき、なかでも BOØWY のメンバーの一人、布袋 寅泰 (1962- ) にたいする影響は計り知れず、徐々にエレクトリックギターに興味をもちはじめていたのである。しかしこの当時、まわりではエレキギターというものが不良少年というイメージが強かったために、仕方なく家にあったクラシックギターを隠れて弾きはじめたのがギターとの最初の出会いであり、わたくしが十五歳のときであった。それはある意味、大好きな音楽、つまり吹奏楽部に入ることができなかったことへのしっぺ返しのようなものでもあったのだ。
そうしてようやく、高校を入学してすぐに、長男の兄とともに御茶ノ水――いわずと楽器店街として有名な場所である――にある下倉楽器店で、五万円ほどの黒いストラトタイプのエレクトリックギターを手にしてからその三年間というもの、日本のポピュラー音楽からロックにビジュアルのコピーに明け暮れ、とくに、友人から教えてもらった D'ERLANGER (1983-1990, 2007- ) 、そして DIE IN CRIES (1991-1995) から kyo - 磯野 宏 (1967- ) を中心に、ビジュアルにのめり込んでゆけば、そのうちに音楽の域をこえ、よくあることのように容姿や行動などにも影響されはじめるほどで、だが、この魅惑はあっけなく終わりを告げることになる。DIE IN CRIES の解散に、当時デビューしたばかりであった GUNIW TOOLS (1996- ) を期に、かれらの音楽とともに「バンド・スコア」などから独学でギターを学んでゆくのは、これが最後となったのである――この当時、幼少のときよりはもちろん、ほかにも聴いていた音楽の様式、アーティストは極めて雑多で、ここでは上記のほかに印象に残っている二三人のアーティストをあげることにした。洋楽ロックでは Randy Rhoads (1956-1982) や、Steve Vai (1960- ) などであったが、代わってライブとなると、母の好みから一九九三年以来は BON JOVI (1983- ) をはじめ、Aerosmith (1970- ) や、Van Halen (1972- ) などであった――。そのようなことになったのも、それと並行していつもの美容室で流れていた音楽に、いかにもといった "JAZZ" が流れていたのであるが、それがなにか人間的で、路地裏のように暗く、しかしときに、摩天楼の錯綜とした雰囲気をもつ独特なリズムとメロディーが忘れられず、わたくしの気に入ったもので、早速レコードショップからサックス奏者で Charlie Parker (1920-1955) から『The 'Bird' Returns (1962)』を購入したのをきっかけに――これが十六歳のときである。全く不思議なことに、それはまるで生まれつき知っていたかのようにそのレコードを選びだし、しかしわたくしは、どこで氏のことを知ったのかは実はわかっていない――、ギターの Wes Montgomery (1923-1968) や Joe Pass (1929-1994) など、演奏者の幅を徐々に広げて聴いたり弾いてみたりとしていくうちに、十八歳をすぎたころにはこれ以上ないというほどに心を奪われていた日本のポピュラー音楽とは、音楽の様式を知れば知るほど、なにかの魔法が徐々に解けていくかのように、少しづつ不思議さと、そうして不気味さと相まって、かれらと業界にたいする異常なまでの「執着」を感じるたびに、ようやく悪魔(快楽)の支配から逃れられたのである。
それはかれらの、ビジュアルやテレビ画面にたいするあこがれと格好よさといった「欲」と「ロマン」にたいする執着で、どこでもそうであるように、ここでもそうであったのだ。結局、わたくしにとって、かれらの音楽――つまりポピュラー音楽全般――とは、魅せる部分によって成り立つ、欲とロマンそのものにすぎず、それは、なにでもなにをしてもかれらが一番であると無条件に思い込むほど、同じように病的に取りつかれ、しかしこれ以上、ロマンに満ち溢れたひとつの『世界』によって、つまりかれらの出す音から、快楽によって「逃避する精神」に支配されてしまうことを良しとしなかったのである。ただ、しかしながら、それがどのようなものであろうと、これも一つの成就された『世界』である。いつの時代でも同じように、ゲーテは「詩と真実 第二部」でこう述べているのである。「(•••)以前には自ら天職だと感じたが、結局他の多くのものとともに棄て去らなければならなかったものが、自分たちの生涯のあいだに他の人々の手で成就されるのを見れば、人類というものはより集まって初めて真の人間なのだということ、それから個人は全体の一員だと感ずる勇気を持つときだけ、喜びと仕合わせが味わえるのだということ、そうした美しい感情がわいてくるのである。(菊盛英夫訳)」これはつまり一体感というもので、わたくし自身も幾度も経験し見てきたことであるが、言葉が完璧に交じり合うという感覚にも似ているだろう。それから、歌手の kyo - 磯野 宏 氏とのたったひとつの繋がりは、青春期の思い出としてわたくしの胸に大事にしまっているのだけれども、かれらをひとりの人間として見ることは、ときにかれらの音やそういった『世界』とは関係なく、会ってみれば普段は見えることのない現実の世界から、先輩としてのやさしさや家族との絆といったものを垣間見ることもあるのだ――もっともそれは自然な形によってのみあらわれるものであるが――そうして、このたったひとつの「偶然」による繋がりは、女性であるひとりの音楽教員によって、その後も大々的にひろがってゆくのであった。
*
さて、ちょうどこのころ、わたくしはあるバンドに入っていたのだけれども、メンバー全員がビジュアル系バンドから脱した、「自分たちの個性的で新しいものを作ろうという志」があったもので、何度かライブ演奏や催し事に出場したりと活動をしていたのであるが、残念なことに、そのうちにメンバーであるかれらの環境や行動などをきっかけに、それはつまり、ここではじめて知ることとなる新興宗教による――日本特有ともいうべきか――芸能と宗教から政治や経済にまでおよぶ、社交にたいする初めて感じた「支配関係」によって――これが何を意味するところであるのかは、『ゲーテとの対話』を熟読している者にとっては分かりすぎるくらいであろう。精神のすぐれた啓蒙を生み出すもの、人間性や道徳的なことも変わらず盲的にさせることは全き世界共通ともいえる――、また、音楽においても、西洋とは明らかな相違点があることに気づきはじめたわたくしは、まだギターの即興の腕も音楽も未熟ということから、自然とお互い離れ離れとなっていったのである。そうしたなかで、わたくしはとにかく「音楽」を知るために、一九九七年に次男の兄に誘われてメーザーハウスへ入学することにしたのである。そこで音楽理論、エレクトリックギターの基礎を 井上 博 、小川 銀次 (1956-2015) に師事することをえらび、クラシック音楽からロック、ポップスに、ジャズ、ファンクなどといったさまざまな音楽とあらためて接していくうちに、エンターテイメントや軽音楽などとはちがった、音楽芸術としての「エレクトリックギター」を探求していくのである。
こうしてわたくしは、四十をすぎてようやく幼年期に止まっていた音楽芸術としての教養が今一度よみがえり、それは、芸術が、芸術そのものとなっている「人間」について語った「永続性」というものから、今さら芽生えはじめたようであるのだが、それというのも完全に虜となっていたポピュラー音楽がそうであったように、ここでも、音楽芸術とは無縁の音楽学校があり、ただ温室的雰囲気のなかで選ばれた機械的人間性と技術、そして業界のうちに経済的、社会的な事のみを重要視した、それはいつの時代でも同じように、「音楽」を仕事として選んだかれらやアーティストの保全のためだけにあるようなもので、芸術および芸術家としての内的な教養と才能は開花することなく、むしろ逆に封じ込められたようでもあり――ひとつ所見を申すとすれば、専門学校のミッションとはとどのつまり機械的な「職人」を育てることにあって、そう、わたくしは職人ではなく、まったくその逆である「芸術」を志していたのだ――、かろうじて、わたくしの感性とリズムを見抜いた先生方の個人的な指導だけは、なんとか自身で活かすことにし、とくに井上先生が教えてくれた Johann Sebastian Bach (1650-1750) から、無伴奏ヴァイオリンで “Presto (BWV1001)” 、そして小川先生との “Blues” からはじまった即興演奏による授業は――氏もまた、生徒と学校との間にある問題を理由からのちに退職したと聞いている――、あの幼少のころに感じえた「歓び」というものをわずかに思い出し、卒業することができたのであった。
ここで、少し話題を変えて差し込むけれども、わたくしが二〇一九年に演奏会の主題としてあげていた、ギター奏者およびピアニストの Shawn Lane (1963-2003) を初めて聴くことになるのは、ベース奏者で Jonas Hellborg (1958- ) のアルバムから『Abstract Logic (1995)』、そして『Temporal Analogues of Paradise (1996)』によるもので、それは、専門学校を入学した年の一九九七年、小川先生の授業で毎回おこなわれた「今日の一枚」に、Jonas Hellborg のアルバム『 e (1991)』を聴いたことがきっかけであった。つまりその後に、 Jonas Hellborg 名義のアルバムを探しだしたことで必然とたどり着いたわけである。そうして一二月してすぐに、有名なアルバム、『Time Is the Enemy (1997)』が発売されたときにはなんとも衝撃的で、渋谷にあるタワーレコードも、その驚異的な演奏からか、棚一面一色に広く宣伝されていたのをおぼえている。しかし結局、Shawn Lane の名は日本同様に世界でもひろく知れ渡るにまで至らずに、病によって二〇〇三年に逝去されてしまう。氏の残したその演奏、音楽性は、初めは誰もが理解できるものではなく、また、誰もが驚愕するものであるが、たとえば、Allan Holdsworth (1946-2017) のような「官能性」とは全く無縁の、一面的で、無機質な知的高ロマンなどとは違い、あまりに人間的で、それはまさしく魔神的、心的事象(ロマン主義)によるもの、有機的事象による動機そのものであり、その官能性と精神は、紙面上や理論上のなかでのみ、正確無比にして音楽が――運動的なものとして――完成されているものと信じて疑わない不毛なる知的妄想にとって、氏の音楽性というものに対しては何らの理解も示さず、むしろそれは無視されるか、迫害されるか以外のなにものでもなく、いなそれよりもむしろ問題は、氏らの即興芸術によって、真に人間的音楽性と技術が周知し、認められることを恐れ、無能なアーティスト、もしくは有識者たちから「羨望」の眼差しをうけることによって、内部で敵手とみなされているのではないか? ということである。さらに逆もまた然りであり、氏の音楽性をまるで神であるかのように崇めることで逃避し、また、そういった技巧的なもの、無調性的、無機質といったような技術的時代の事象による精神を信奉することで、それ以外の人間性といったもの一切を避け、飽くことなく誹謗し、まるで亡者のように群がる人々においては、音楽芸術の発展など到底見とめるわけがないのである。しかし、これはあくまでわたくしの所見であって、氏らの残した音楽性の意義と意味は、夢や現実に逃避したいわゆる「ロマン」の人同様に、こうした全人的なものから逃避した馬鹿げた不毛な「主義」によって、飽くことなく誹謗され、またたく間に排斥されるようなことは、再三あってはならないことなのである。残念ながらわたくしのまわりでは、氏らのような即興芸術の継続を願う人々の圧倒的少なさと理解力の乏しさ、また逆に、その圧倒的技巧によって、後進の育成などまるで無価値であるかのように、それは無条件に後進を貶め、排斥せしめてしまうというのは、繰り返される世の常というものを感じざるをえないのである。こうしたことから、むしろ氏らにとっても、わたくしも含め、「ロマン」という一面性から生まれ出た信奉者たちから逆に「ロマン」扱いされるということは、ここでも逆に一種の名誉称号――*フルトヴェングラーの金言――としていえるだろう。そういったことからして、わたくしのギタープレイはより深さを増してゆき、音楽芸術としての可能性からも、Shawn Lane からならった「即興芸術」による音楽を目指していくことになり、こうして学校を卒業してから、三年後の二〇〇三年六月十六日に、ライブ演奏を展開してゆくのである。
*詳しくは、Wilhelm Furtwängler -フルトヴェングラー (1886-1954) 『音と言葉』から論文「ロマン主義への省察(一九四三年)」を参照のこと
ちなみに余談ではあるが、わたくしのライブ演奏は最初、ドラムスにシーケンサー(MIDI)を用いており、そのドラムスのパターンは、すべてわたくし自身が制作していた。こういったことから、音楽のテンポとリズムの強化、そうして即興演奏に欠かすことのできない、リズムに対するすぐれた柔軟性と対応には、大いに役に立ったものである。さらにもう一つ、この場を借りて申しておかなければならないことがある。わたくし自身、アルバムを二〇一七年までに三枚ほど個人でリリースしているが、すべて失敗作として、破棄したということである。理由は曲が作れていないこと、そして、演奏会のときとはまるで別人のように、「レコーディング」となると、ほんのわずかしか「音楽」を内部から演奏することが出来なかったからである。つまり、この「音楽」を演奏するうえで、本来そこにいるべきはずの共同体としての「聴衆」がいないのである。自分が楽しみ、自分のために演奏しているのであればなおのこと、まさしくこれこそ真の高ロマン主義の在り方といえよう。音楽芸術は、絵画や彫刻の世界とは全く別のものなのである。それではわたくしは何のために録音しているのかといえば、今は記録と記憶のためであると申しておこう。
*
考察
わたくしの論稿および言葉において、幾度も記述されているようなことではあるが、芸術および芸術家にとって、それだけこの電子楽器、メカニカルというものは大変にすぐれた武器でありながら、本質的にすでに自立しているものであり、有機体生命である人間には極めて不自然であることが逆に支配されやすく、とくに児童から青年期にたいして、われわれがコントロールを誤ればたちまちにその本領を発揮し、ゆえにそれは歪、誘惑し、精神をたちどころに無能化し、意識そのものからメカニカルによって支配されてしまうということである――世界考察によってロマンにまみれた周囲の技術的、科学的による環境の変化のひとつである。このことによって、まさしくわたくしは国家の保護によって、内部で温室植物そのものとなったのである。しかし、今こうして「音と言葉」にたいして献身的でいるのはどういうわけか? それはほかならぬ両親の、とくに母の偉大で献身な支えがあってのことだということを理解してもらわなければならない――。つまりこのことから明治維新、戦後にかけ、われわれ(日本)の伝える音楽や文化、身近なものからそのほとんどが当たり前のように西洋から伝わった文化によるもので、ゆえに本来、古来より日本や中国で根付いた古典、とくに文学、そして体験から学ぶべき東洋の精神性(克服)を無意識のうちに放棄し、喪失してしまったのである(されたといっても通じるだろうか)。こうしてわれわれは、西洋と対当すべく、ロマンによってのみ生きることを選択したことで、さまざまな現象から簡単にメカニカルに支配されやすくなり、それは比較化され、あらゆるものはリスト化し、とくにこの世界考察という意味での「科学的思考」は、戦前から戦後にかけ(大東亜戦争のこと)、物事を超越した立場をとることで、われわれを現実から切りはなし、考察させ、理解させることから、「ロマン」の不毛性を深く内部に宿してしまったということがここでようやくわかるのである(このいつものくだりは、Wilhelm Furtwängler -フルトヴェングラーの対談『音楽を語る(門馬直美訳) - Geepräche über Musik (1949)』から、第六章《環境と芸術》にならっていることを付け加えておく)。
こうして自立した『世界』は(これを女性的なものとした上で)、国家の保護によって、精神世界および芸術の内部から人造人間「温室植物」を作り出してしまい、これを『世界』は==食いもの==として利用しはじめたというのである。つまり結局のところ、自ら立ち上げたスローガン「自分たちの個性的で新しいものを作ろうという志」これ自体が、病的な「高ロマン」を生み出しつづけていたのである。わたくしは、二十三歳ごろを境に、徐々に漫画やアニメ、ポピュラー音楽やゲーム、そういった戦後の日本で培われた現代文化とは趣味の域を脱し、企業や組織もひっくるめた「かれら」をひとつの『世界』、そして、ひとりの「人間」としてみるようになっていったという訳である。もちろん、芸術を創造することにおいて、わたくし自身も含めた「かれら」も、ロマン主義(ロマンティシズム)であることは至極当然のことであり、極めて重要なことであるがしかし、『世界』の「ロマン」と西洋の「ロマン主義」とは、全く別の性質であり、西洋のそれは、古来よりの根強い「古典(クラシック)」があってのロマン主義であって、この二つの形式を思慮深く利用して発展させたことは、偉大な芸術とともに生きるかれらの共通の原初である Johann Sebastian Bach を指針として再発見したということでうなずけるであろう。そしてまた、フルトヴェングラー がこの宗教音楽家を、ロマン派に絶大な影響を与えたという意味から、最大のロマン主義者と呼ぶのも至極当然のことなのである。
しかし戦後、後期ロマン主義最後の人、フルトヴェングラー の警笛はとどかずに、『世界』は大洋の歯車を回しはじめ、現実からのあらゆる「悲劇」を技術によって内部に閉じ込め、さらに、あらゆる独自の世界観と人間観を作りあげてしまったかれらの保全のためには、「夢のロマン」、そして「知的妄想の高ロマン」による幻影と逃避からつくり出される混沌とした発展が必要不可欠であり、こうして本来あるべき教養(古典)としての芸術、そうして、感性と知性との均衡は、すべて紙面上にまとめ上げられた、『世界』のリスト化された題材としての質料(悲劇)だけが機能してしまったというわけである。今ここで、すでに経済、社会において、『世界』のために独自の世界観と人間観を作りあげてしまっている多くのアーティスト(温室植物)および人類にたいして警笛をならすとすれば、先ほども申したように、業界も民衆も一緒になって二種のロマン主義を食いものにしているということである。そういったことから世代の移り変わりによって、われわれとは『世界』がつくりだした 「悪魔の神像」に満たされるべき卑俗によって生みだされたもので――なるほどわたくしがここで攻撃的であるのも『ゲーテとの対話』にある「どうせ俺たちみなアダムの出」ということである――、こうして深く根付いた「ロマン」にのみ生きるアーティスト、つまり人類は、必然と業界と民衆とのジレンマから自滅してゆき、ストレスなどから一定の能力を超えたとき、さまざまな社会問題に事件、不快や不信、そして、芸術とは一切不要な戯言が絶えなくなるというのはこういったことからで、不滅のロマンを歩むわれわれ人類にとって、永久に避けることのできない運命の様である。これはあらゆる現代社会においても、どの様な国々にも無条件に関与してしまうことで、アーティストのなかでもっとも顕著にあらわれた例では、Michael Jackson があげられるだろう。そして、この悪魔のロマンの最大かつ最も憂慮すべきは、善悪問わず、犠牲そのものが必ず無意識のうちに、もしくは本能的に「欺瞞」につながってゆくという人間性である。百歩譲ってこの『世界』の病的ロマンが許されるのは、精神面においても、まだ古典を知らない子供たちだけである。
ではこの「人間的なもの」からわれわれは一体なにをすべきか? これらの考察は決して大衆向けではなく個々の問題であって、後述するが、これらの攻撃的な考察から「戯言」として読まれるのか、それとも「省察」によって読まれるのか、こうしてゲーテと同じく「アフォリズム」によって仕向けたのが、今のわたくしの、中立としての==義務==なのである。ひとつだけ申しておくと、われわれ芸術家が望んでいることは献身であって、組織はこれを理解することである。「祖国」にたいする愛情は、真の意味において、「芸術」から原点に帰するのである。人間でいうところのつまり、「純愛」である。
この「祖国」を愛するとはどういったことで、祖国とは一体なにを意味するのか? 映画やアニメなどによってさんざんに見せられていることだが、ここは代わって、 Johann Peter Eckermann (1792-1854) による『ゲーテとの対話 - Gespräche mit Goethe(1836-1848)』から、一八三二年三月に記述があるとだけお伝えして置く。われわれは幾度となくいみじくも、同じことを伝えつづけているのだ。
「世なれた実務家よ、あなたは人間を悪だと考えている。しかし、それはまちがいだ。世間知らずの夢想家よ、人間を善だと考えたら、かならずきみは裏切られるにちがいない。」
- Johann Wolfgang von Goethe. / 参考にした訳書は次の通り。/『ゲーテ全集 十一』«初版» から「ゲーテ格言集 社会と歴史」、人文書院、大山淀一訳、一九六一年(昭和三十六年),pp.一二〇頁に詳しい。
_______
第三章:二十五才~修羅 まさしく、古典を避け、あらゆるロマンにのみ生きるものにとっては不快で不気味な考察が長引いてしまったが、さて、そろそろ短篇の回想および考察はここまでにして、先ほどにも登場したドイツの指揮者、音楽家および芸術家として著名な ヴィルヘルム・フルトヴェングラー との出会いについて話しを進めるが、それはいつだったかにテレビで放送されていたドキュメンタリー映像によって知ることとなる。その後、氏の著作が新装版として出版されるとの情報をどこかの専門誌で見聞きしたのをきっかけに、一九九九年に興味本意で買った一冊の本、『音と言葉 - Ton und Wort (1954) 』がそれである。これが当時のわたくしには大変にむずかしく、わたくし自身、より決定的な経験と体験によるものを強く必要としていたのであるが、このことで、仮にもしこれが「思春期」のことであったとすれば、つまりそう、これこそが何物にもかえがたい魔神的(デモーニッシュ)なものであって、最も全人的な意味において、教養としての芸術のかてとなるのであるとしたら、いやしかし、そこで人はなにを体験し、経験してゆくのかは、わたくしの知るところではないのだ。しかし、Friedrich Wilhelm Nietzsche (1855-1900) のいう「泡立ちあふれる生の象徴としてのみ、芸術において意義と価値とを見出す」というのであれば、それは前述にも申したように、二〇一六年までの間に幾度も繰り返されてきた悲劇とともに、経験と知識、体験によって、ふと思い立ったように棚に眠っていた『音と言葉』を読み直してからというもの、不可解であったことがまるで嘘であったかのように感銘を受け、その後、自身ではじめての論文『オラ - OlaⅠ ――ヴィルヘルム・フルトヴェングラーの論述に基づく圏谷の星々(西暦二〇一七年――元号・平成二十九年)』を執筆することと相まったというのである。
「(•••)こうしてその後すぐに、この物語はまるでなにかの「魂」に導かれるかのように、わたくしにとってそれはまるで『ファウスト - Faust (1808, 1833) 』を思わせる試練として、その「美しい人」との必然的出会いは、今一度、悲劇(古典)と喜劇(ロマン)とともに「永遠なるもの」を自身によって求めたことから、"The Count" を題としてあげたのだ。この『世界』と不滅に共存している孤独な人ならざるもの「不死者 - Nosferatu」は、二〇一七年の五月に、わたくしの生涯と死後にたいする象徴として、"Tarot" 七十八枚のうちに出現した『死神 - XIII』を、このノスフェラトゥ - Nosferatu "D". に結びつけたのがすべてのゆえんである。あとのことは後述をもって説明といたし、わたくしは今、八つのときに内部で息絶えたはずの「ロマン」に、もう一度あの小さく輝く、高貴な白き花に導かれながら、刻の針をまわし、「前進」し「進歩」してゆこうとしているのだ(•••)」 第二部へつづく、
-------
言葉の肖像Ⅱ 断片 回想録 |リリスとの対話 1994年: ******* ――こんなふうに断片としてわたくしの二部ははじまってゆくのだけれども、それぞれの苦難は予期した通り今まさしくわたくしにはね返り、数々の憂いは、二度ならず三度のあの二〇一八年の耐え難い突然の悲劇的な破局によってリリスは目覚め、世にも珍しいわたくしの詩は、音楽などを通じてすでに始まりを迎えているわけだが、その二〇一四年から一八年に起った新たな二人との出会いもまた、隠されたリリスとの対話として小冊子やSns (serpents) などから僅かではあるがすでにいくつか記録されている。 この二部の断片が次にいつ始まるかはまったく未定であるが、わたくしはとにかく幼少のときより計算もさることながら様々なことに追い付くのが遅いたちで不器用であるのだろう。 こうして、自らの罪を贖うために、そして、麗華のわたくしへの純真な愛は、この残された誕生日プレゼントを深い憐れみとして、ともに大事に、大事に胸にしまっているのである。 ******* [...] ああ、1994年、わたくしはそのとき、知らずのうちにとても残酷で、とても冷酷な人間になっていた。北欧の地から届いた麗華の深い愛に満ちた一通の手紙に、わたくしはどうすることもできずに、無情にも何も考えることもなく過ごしてしまっていた。今思えば、そのときからどれほどの孤独と苦痛を彼女に与えてしまっていたのか! それはとても恐ろしく、取り返しのつかないことをまだ十代という若いうちに与えてしまい、わたくしはここで早くも完全なる大罪を背負ってしまったのだ! そして、さらに麗華への冷酷さはますます深めていったのである。 「それは当然さ! ぼくのことを好きでいてくれた麗華とどのようにお付き合いしてゆけばよいのか全く分からなかったんだ! なぜならぼくにはまだそのとき、一年前に一度ふられたにもかかわらずに、その子がまだ好きでいたからなんだ。それなのにぼくは、君と交際してしまった。しかも君は、ああ、こともあろうにぼくと交際するまでにどんなに君は悩んでいたことか!」 わたくしはそれを知っておきながら愛に応えずに無情であった。その時点で麗華の、真の愛をわたくしは裏切、見捨ててしまっていたのである。 こうして一度目の付き合いは自然消滅という彼女にとって悲しく、孤独で、おそらく耐え難い苦悩によって、これらを与えてしまったわたくしは、憂いとなり永久に呪われし定めとして、二度目の彼女との再会とは、そう、死の女神は文字通り一種の「死」を、わたくしに吹き与えたのであった。[...] ➖
*******
-ミニョンに寄せて-
「谷を越え川を越え きよらかに日のみ車が走ります ああ 日は日ごとにめぐりつつ あなたの悲しみ 私の悲しみを 心の奥ふかくに 朝ごとにまた目覚ませます |
Contact: YOJI ITO
© 2026 MASTERBUILDRECORDS. ALL RIGHTS RESERVED.